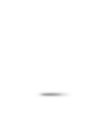酪農と聖書④ 「愛と感謝」をもって動物利用をするべき
掲載日:2019.02.06

酪農学園大学獣医学群
獣医学類(獣医倫理学)准教授
髙橋 優子
酪農学園大学には「動物記念 祭」という行事がある。筆者も2015年から同記念祭の司式を担当している。本学での実験や病院で亡くなった動物たちを記念し、“感謝”を表すのが目的である。動物には、もちろん牛も含まれる。同じような行事は、日本中の動物実験施設を持つ機関や動物を展示する場所などでも行われている。しかし、大抵の場合は「動物慰霊祭」という名が付いている。本学ではなぜ「慰霊祭」でなく「記念祭」なのかと思われる向きもあるだろうが、それは本学がキリスト教主義を基礎としているからである。
キリスト教では伝統的に動物には“霊”がないと考えてきたので、あえて「慰霊」という言葉を避けて「記念」としたのであろう。ちなみに人の場合でも、キリスト教会では「法事」の代わりに「記念会」というものを行うので、“記念”という言葉は取って付けたようなものではない。
それではなぜ、キリスト教では動物に霊がないと考えるのであろうか。筆者は『獣医倫理学』という分野を研究するようになり、いろいろと調べてみた。すると、聖書には「動物には霊がない」という記述は存在しないことが確認できた。むしろ、通常“霊”と訳されるヘブライ語「ルーアハ」が動物にも使用されていることも分かった。聖書に直接的な根拠がないからには、別のところからきているのである。
キリスト教の伝統は、中世に大きな転換点を迎えた。有名な神学者トマス・アクィナスが『神学大全』(中世ヨーロッパの神学書)を著したのだ。それは当時、イスラム教徒がアラビア語に翻訳して読んでいたギリシア哲学、特に古代ギリシアの哲学者アリストテレスの著作に影響を受けて成立したものである。それまでヨーロッパではギリシア哲学は忘れられていたのであった。
アリストテレスの考え方によれば、“存在”には秩序がある。つまり、高次の存在もあれば低次の存在もある。大まかにいって、神を入れる場合は“神”が最高位であり、その次が人間である。その後は動物、それから植物、最後に無機物がくる。この“存在の序列”が中世に、『神学大全』を通してキリスト教の伝統に決定的に組み込まれたのである。
もとより聖書は、人間が善良な管理者として、動植物を含む自然に対して節度をもって保持することを求めている。その意味では、動植物より人間を上に見ているといってよい(興味深いのは、聖書では神に仕える“天使”も人間より下と考えられていることである)。しかしながらそれは、あくまで善良な管理者の義務であり、自然を意のままに搾取する権利ではない。
私たち人間は、動物を食べたり、展示したり、ペットとして愛玩したり、実験したりする。キリスト教的には、それ自体に罪悪感を持つ必要はない。ただ不必要な、あるいは過剰な動物利用をしないように留意せねばならないのである。「愛と感謝」をもって動物利用をするべきなのである。それが、酪農学園大学構内の「動物之墓」に“愛”と記されている理由だといえる。