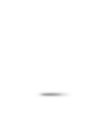ランピースキン病に備えを
掲載日:2025.02.14
酪農学園大学
名誉教授 佐々木 均
はじめに
昨2024(令和6)年11月、福岡県で牛のウイルス病であるランピースキン病(以下「本病」という)を発症した牛が我が国で初めて確認されました。その後12月までの間に、熊本県へも拡大し、両県合せて20余の施設で感染が確認され、感染牛の淘汰や未感染牛へのワクチン接種などの対策が講じられました。気温の低下とともに、主な媒介者と目されているサシバエの活動が低下したこともあり、2024年12月26日以降、新たな感染は報告されていません。しかし、春を迎え暖かくなると、媒介者の吸血昆虫の活動が活発化し、再度本病のウイルスが侵入した際には、昨年末以上の感染が起こる可能性がありますので、冬の今の時期から対策を講じて、本病への備えを万全にしておきましょう。
ランピースキン病とは
本病は、ポックスウイルス科カプリウイルス属ランピースキン病ウイルス(以下「LSDV」という)に感染して起こる牛と水牛の病気です.1929年にザンビアで初めて報告され、サハラ砂漠以南のアフリカの風土病と考えられていましたが、2010年代以降、中東、ヨーロッパと分布を拡大し、2019年からはアジア諸国でも発生が見られるようになりました。LSDVは皮膚病変、唾液、鼻汁、乳汁、精液などから検出され、子宮内の胎子にも感染します。LSDVに感染後、牛は4~14日間の潜伏期間を経て発症します。感染牛に発熱、鼻漏、流涎、食欲不振、泌乳量低下をもたらし、臨床症状は、不顕性のものから表在リンパ節の腫大や皮膚および粘膜に病変が現れる重篤なものまで様々です.皮膚の病変部は、最初のうちは硬く盛り上がる程度ですが(図1a)、その後直径1~8cmの完全に肥厚した結節に発展します。結節は特に、頭部、頸部、乳房、生殖器、会陰部などの、体毛がまばらなところに確認されます。牛によって、結節が数個しか確認されない個体や、全身を覆うほど多数確認される個体もあるなど、幅があります。結節の多くはその後、表・真皮および皮下組織やその下の筋肉にまで達することがある本病に特徴的な逆円錐状の壊死巣を形成します(図1b)。壊死巣はその後皮膚に穴を残して脱落しますが(図1c)、それは、乳頭・乳腺の損傷、跛行や雄牛の恒久的不妊、雌牛の流産と言った二次的感染の基になる場合があります。ほとんどの牛は数ヶ月で回復しますが、皮膚病変の程度によっては数年を要することも知られています。なお、これまでに本病に対する治療法は開発されていません。
2024年に福岡県、熊本県で発生したランピースキン病
LSDVゲノムの一部領域(RPO30:606bp)の動衛研による解析では、我が国の本病ウイルス株(福岡1~9例目、熊本1例目)は、中国、台湾、韓国株を含むアジア流行株と100%一致したことから、LSDVを保持した吸血昆虫が、周辺国から風に乗り、又は船舶等に運ばれ我が国に侵入し、本病の感染を引き起こしたと考えられます。また、国内での感染拡大要因の大部分はサシバエ等吸血昆虫によるものと考えられますが、熊本の1例目(国内3例目)については、福岡県の発生農場から導入された牛に起因する事が確認されています。福岡県17 例目(国内18 例目)については、福岡県の主な発生地域から約35 ㎞離れた農場での発生でしたが、これはサシバエ等吸血昆虫が車両等に迷入し遠隔地まで運ばれた、又は発生地域から風に乗り飛来した可能性があると考えられています。また、アジア流行株は従来の株に比べ、接触感染能が増強されているという海外からの報告があるものの、主たる感染経路については、従来の株同様吸血昆虫であるとされています。
飼養者が行うべきサシバエ等媒介昆虫対策
これまでに海外から報告された媒介動物の多くは昆虫で、その中でも、サシバエ(図2、3)やカ、アブが重要とされています.また、吸血するマダニも媒介するとの報告もあります。カは幼虫が生息する水たまりが無ければ発生できません。ですから、カ対策の基本は、不要な水たまりをなくすことです。堆肥場周辺にできた轍(わだち)にたまった「れき汁」はアカイエカの、古タイヤ・空き容器そしてブルーシートのくぼみにたまった雨水はヤマトヤブカやヒトスジシマカ(本州以南)などの産卵場所兼、幼虫の格好の生息場所になります。見つけ次第たまり水を抜くことを心がけましょう。アブはカと違って幼虫が自然環境に生息していることから幼虫対策は難しく.そこで、成虫の襲来回避が対策の中心になります。そこでとられるのが、畜舎の開口部を薬剤が練り込まれた樹脂で織った目合い6 mmの防虫ネットで塞ぐ(図4)、牛の両耳に蒸散性薬剤含有樹脂製イアータッグを装着する(図5a)、牛体にETB乳剤など休薬期間の無い殺虫剤を用法用量を遵守してスプレーする(図5b)などです。これはサシバエの成虫対策にも効果がありますので、是非検討してください。サシバエの成虫対策として捕虫紙を壁などに貼って、成虫を捕獲することもあげられます(図6a)。海外から、捕虫紙の周囲を黒く縁取ることで、捕虫数が増えるという研究結果が報告されています。試してみる価値がありそうです。
サシバエの幼虫対策の第一は、何より産卵される培地でその後幼虫の生息場所となり、餌となる排糞の処理です。サシバエは、糞そのものよりも、糞に敷料や飼料残渣が混じって腐敗した、いわゆるたい肥に好んで産卵します。ですから、牛舎の隅々まで清掃を徹底しましょう.もちろん敷料は全量交換し、牛床に残らないようにすることが肝要です(図6b)。壁際、ウォーターカップの下、通路に敷かれたゴムマットの下や継ぎ目などに残った排糞もサシバエ幼虫の餌や生息場所になります。その中でも特に注意して清掃してほしい箇所は、バーンクリーナーとその尿溝です。定期的に高圧洗浄水で、そこに付着した糞などを洗い流すようにしてください。牛舎から搬出して、たい肥場に集積しているたい肥は、発酵熱でたい肥の中に生息している幼虫などを殺虫するよう、定期的に切り返して発酵を促進してください(図7)。また、その際、昆虫成長制御剤(IGR)を混和することも効果を高めます.蛹になる直前の幼虫は、蛹化場所となる乾いた場所を探して、たい肥から移動します。ですから、たい肥場のたい肥盤を囲むように、尿溜めに繋がる、幅と深さが10 cm程度の水を張った溝を設置して、幼虫の移動を防ぐ手立てを講じることも、サシバエの発生抑制効果を増すことになります.定期的に溝の水を抜いて交換することで、ハナアブ幼虫(オナガウジ)やカの対策にもなりますから、忘れずに実行しましょう。
また、発生農場周辺地域からの資材や車両等については、農場内や消毒ポイントなどで、殺虫剤等を車内や積み荷に噴霧することが推奨されます。これには、液化二酸化炭素に薬剤を溶かした製剤が適していると思います。
飼養者と獣医師による医原性感染拡大防止対策
注射針や直腸検査用手袋等の使いまわしは、本病のみならず牛伝染性リンパ腫(EBL)等他の伝染病の感染拡大を引き起こす可能性が高いことから、必ず1頭ごとに使い捨てとしなければいけません。また、妊娠鑑定等のために超音波診断装置のプローブを直腸内で使用する際も、カバーで覆い1頭ごとにカバーの交換をする必要があります。加えて、本病については、感染牛に対し使用した器具を介して感染が拡散する可能性があることから、発生が確認されている地域においては、観血的な治療、削蹄や除角、耳標装着等に用いる器具等を一頭ごとに洗浄・消毒する必要があります。なお、同日に発生農場と非発生農場を診療する場合は、可能な限り非発生農場から発生農場の順に行うことが推奨されます。
ランピースキン病発生時における対策
早期とう汰、ワクチン接種、吸血昆虫対策が、対策の三本柱と考えられていますので、サシバエ等吸血昆虫対策を継続しつつ、ワクチン接種を躊躇すること無く実行するとともに、感染牛を速やかに淘汰するようにしてください。なお、ワクチン接種後3週間経過した子牛において、臨床的な異状がない場合には、その子牛が移動先に本病をまん延させるリスクは低いと考えられます。さらには、本病は、吸血昆虫を介した間接的伝播が主な感染経路ですが、海外では、実験的に感染牛と同居していた牛に接触感染した例も報告されていますので、発生農場においては、発症牛を速やかかつ適切に農場内で隔離することが必要です。家保やNOSAI、農協など指導機関の指示に従って、本病感染拡大阻止に務めてください。
上記は、筆者が衛生昆虫学の専門家としてオブザーバー参加した、2024年12月26日に農水省で行われた「ランピースキン病対策検討会」でまとめられた提言や海外で報告された論文等を基に解説したものです。








 この作品はクリエイティブ・コモンズ 表示-非営利 4.0 国際ライセンスの下に提供されています。
この作品はクリエイティブ・コモンズ 表示-非営利 4.0 国際ライセンスの下に提供されています。