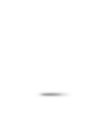日本における搾乳ロボットの普及と地域による利用特性
掲載日:2020.10.27
酪農学園大学 農食環境学群 循環農学類
教授 森田 茂

はじめに
搾乳ロボットという一つの道具が中心となり、搾乳ロボットを使った酪農場での生産システム(自動搾乳システム)へと変遷しました。酪農技術が普及すると、最初の想定を越え、社会的背景や酪農場の特性に合わせ、利用方法の改良が利用者である酪農家の手で行われます。ローカルルールともいえる利用法は、いつか世界的に通用する技術として飛躍することがあります。
1.搾乳ロボットの開発と普及
搾乳作業の自動化に関する研究は、当初、作業の省力化と日常的作業からの解放を目的として開始されました。酪農場の1人当たりの平均労働時間は、2015年度で2,200時間/年でした。他産業を含めた労働環境の変化や、ゆとりを生み出す作業体系の推奨(「働き方改革」)などの社会状況変化(働き手の確保)と関連して、“作業をロボットに任せ、人間はコンピュータの設定などを行う”といった変革が酪農場にも進展しました。搾乳作業の自動化に関する研究と自動搾乳システムの普及は、そうした社会的背景が重要な鍵でした。このため搾乳ロボット普及には、世界的な地域差があります。
時代をさかのぼれば、搾乳作業の自動化(搾乳ロボット)の開発に関する研究の嚆矢は、わが国の農水省畜産試験場において1970年代になされました。こうした日本での研究を契機に、世界的にも自動搾乳に関する研究の初期には、乳頭位置検出やティートカップの装着に関する研究が行われました。ただし本格的な自動装着技術の進展には、センシング技術やそれを処理するコンピュータ技術、ならびに機器の動きの制御技術の発達が必要でした。
酪農場への普及にかなうレベルに達した後も、センシング速度や装着速度の向上に関する研究は、搾乳可能頭数と直接結びつくことから、継続して進められました。現在に至るまでの、センシング技術の向上は目を見張るものがあります。これに併せ、機器の動きの滑らかさや騒音レベルの低下、牛の進入方向・滞在位置の変更など、牛の動きに影響する改良が施されます。
搾乳ロボットを実際の酪農場に導入するため、自動搾乳技術を応用した新たな飼養管理方法の検討が進展を始めました。開発の中心がヨーロッパであったことから、配合飼料給与装置(フィードステーション)を搾乳場所として利用することが提案されました。このことは、それまでの一定時刻での全頭の搾乳という概念を否定し(不定時搾乳)、さらに多回数搾乳への道を開くという、管理システムの劇的変革でした。こうした飛躍が、搾乳ロボットという道具を、それを中心とした自動搾乳システムへと導きました。
日本においては、帯広畜産大学に最初の実用型搾乳ロボットが導入されます(1993年)。現在最も普及しているLely社製の搾乳ロボットが、民間牧場初号機として導入されるのは1997年です(北広島市馬場牧場)。それから20年を経て、2019年10月現在では、500戸を超える農場に1,000台を超える搾乳ロボットが導入され、その普及スピードは極めて速いものです(2017年330戸の農場に560台に比べて2年間で2倍の導入台数となる)。日本全体でみれば3%の酪農場が、北海道内に限れば、6%の酪農場が搾乳ロボットを利用していることになります。
2.搾乳ロボットを使った飼養管理システム
酪農場における搾乳方式のうち、搾乳ロボットは「牛が動く」システムに区分されます。中心的に開発を担ったオランダでは、放し飼い方式での飼養が中心でした。牛が動くシステムでの利用が、「パーラー代用型利用」と「24時間稼働型利用」として、自動搾乳システム開発当初から想定されました。1990年代に「高価な搾乳ロボット」を、「それほど大規模でない酪農場(せいぜい120頭)」に導入する場合に、ロボットを24時間稼働させて、乳牛を1日中訪問させるというシステムが主流を占めることとなり、牛を動かす手段の一つとして、ゲートシステムに基づく新たな牛舎設計が提案されました。
一方で、ゲートシステムは採用せず、これまでのフリーストール牛舎のように牛舎内を自由に移動できるシステム(フリーカウトラフィック)も研究されています。これは、牛舎内で給与する混合飼料(基礎混合飼料:PMR)を牛群の養分要求量より低めに設定し(薄い濃度の餌を与え)、搾乳ロボットで給与する濃厚飼料量を増やし、これをモチベーションとして乳牛の訪問を促すシステムです。
ただし、搾乳1回当たりの給与量には上限があり、多量の濃厚飼料を搾乳時に給与するのは、ルーメン発酵の異常や乳牛の健康に悪影響を及ぼすことから行うべきではありません。具体的には、1回の搾乳当たり2kgが濃厚飼料給与量の限界であるともいわれています。個体ごとの1日の搾乳回数を4回とすれば、日量8kg程度が、搾乳ロボットで追加給与できる濃厚飼料給与量の限界となります。
搾乳ロボットは濃厚飼料給与装置でもあるため、搾乳回数を増やせば追加給与できる濃厚飼料量は増加できる仕組みになっています。しかし、搾乳回数は個体ごとの乳量と連動し、8kg以下あるいは6時間以下での搾乳は乳質低下の原因になるため、簡単に搾乳回数を増加することはできません。また、搾乳回数を増やせば、搾乳ロボットの利用効率が低下するため、ロボット1台当たりの生産性を考慮すればむやみに搾乳回数を増加することはできません。
つまり個体ごとの濃厚飼料給与量の調整には限界があり、高泌乳牛や分娩直後の時期には、PMRからの栄養補給が、乳量増加、繁殖成績の向上、乳牛の健康向上のいずれにも共通した飼料給与計画上の鍵になります。十分量の飼料給与(PMRの残飼が5%以上)や自動餌寄せ機の活用、嗜好性が高く採食量が確保される良質粗飼料の利用が重要となります。また、こうした栄養補給の課題は、乳牛の繁殖関連で問題となるため、乾物摂取量を十分に確保しているかどうかを「採食状況モニタリング(反芻活動、ボディコンディションスコア)」をセンサー活用して積極的に行い、その結果を飼養管理に活かす仕組みが開発されつつあります。
自動搾乳システムでのPMR技術は、TMR(混合飼料)技術から離れて進化しています。搾乳ロボットでの濃厚飼料給与量とPMR濃度のバランスが、牛舎内での牛の動きを制御する技術であり、自動搾乳システム運用上の成否の鍵となっています。繰り返しになりますが、単独給与でも十分な採食量のある良質粗飼料確保こそ、自動搾乳システムを円滑に運営する最大のポイントです。このことが分かり、適切な粗飼料確保できれば、PMR設計は訪問回数を見定めながら、適宜、変更可能となります。
一つの装着アームで複数の搾乳ストールを持つ、いわゆるマルチタイプの搾乳ロボットの開発は、対応できる頭数規模の柔軟性や、搾乳ストール当たりの価格の低下などから期待されました。しかし、現実には様々な運用上の理由から、シングルタイプが普及することになります(写真1)。一つの酪農場に2台以上の搾乳ロボットを導入する際に、乳牛群を分割し1群1台として60頭程度で利用する方法が、普及当初は採用されました。現在では、シングルタイプの搾乳ロボットを1乳牛群に2台設置することが多くなっています。
最近では、酪農場の超大型化時代をむかえ、マルチタイプの発展型ともいえるロータリー式搾乳ロボットが、搾乳人員の軽減を目指して開発・導入されています。例えば、年間1万トン出荷のいわゆる“メガ・ファーム”を例に考えれば、1群2台のシングルタイプ搾乳ロボット利用では、24時間連続稼働型利用させても、少なくとも12台の搾乳ロボットが必要となります。ロータリー式搾乳ロボットでは、1時間に100~300頭の搾乳が期待されています。この通りであれば、3~4時間で1回の搾乳作業を終了できる可能性があります。
搾乳機装着のために搾乳ロボットをロータリーに導入するシステムでは、個体ごとに、乳量に応じて搾乳回数を設定するのは不可能です。また搾乳時の負担は大幅に軽減されますが、搾乳のために牛を待機場へと誘導する作業(牛の追い込み)は必要なままです。
3.搾乳ロボット普及とともに進む飼養管理システムの改良
1990年代に酪農場での導入が開始された自動搾乳システムは、全産業における作業の自動化、IT技術の普及および通信インフラの普及やコンピュータ端末の大衆化(スマートフォン)などとともに、大きく進展しました。
現在世界では4万台以上の搾乳ロボットが稼働しているとの指摘があります。前述のとおり、2010年以降、わが国の酪農場でも搾乳ロボット導入が急速に進んでおり、稼働する搾乳ロボットは1,000台を超えているものと思われます。搾乳ロボットの導入がヨーロッパを中心に進んでいたことから、多くの場合、飼養管理方式を「フリーストール牛舎、中程度の乳量(日量30kg程度)、補助搾乳施設無し」に合わせていました。わが国での搾乳ロボットの普及も、こうした条件下で考えられてきました。
搾乳ロボットの世界的普及に伴い、こうした利用法は、世界各地の状況に合わせ変貌を遂げています。たとえばオーストラリア・ニュージーランドでの搾乳ロボット利用は、放牧なしでは語ることができません(写真2)。アメリカ中部の北海道とよく似た条件の酪農地帯では、高泌乳化への対応が検討されています。つまり、地域的特徴をふまえた飼養管理システムの改良が、搾乳ロボットの普及とともに進んでいるのです。繋ぎ飼い牛舎への自動装着技術の適用も現実となりつつあります。海の上に施設を浮かべ、自動搾乳システムで搾乳を行う試験的な酪農場も登場しています。
日本国内でも、地域により様々な条件で酪農が行われています。こうした農場ごとの特殊性に合わせて、ロボット搾乳の飼養管理は変化しています。例えば、平均日乳量が45kg以上で、ロボット1台当たり65頭を超えて飼養し、1台当たりの生産日乳量が3,000kgを超えるような農場も現れています。これは、世界でも例を見ない独特の形態であり、注目する関係者も多くいます。実は、“搾乳ロボットが1日に何回ぐらい搾乳できるか”はある程度分かっていますが、“何頭の乳牛が飼えるのか”は、乳牛群内の社会行動とも関わっており、よくわかっていません。頭数の増加は1頭当たりの訪問回数を減少させることは明白で、訪問回数の減少に伴う搾乳回数の減少を避けるため、朝夕の作業時に、搾乳可能牛はすべて誘導するといった特殊な飼養管理を行うこともあります。
おわりに
日本国内でも搾乳ロボットはさらに普及し、様々な条件で活用されると考えられます。国外の事例も考えれば、思いもよらない形態で利用される事例も現れるでしょう。これまでの導入事例では、搾乳ロボットの飼養管理に、酪農現場が合わせることが多くありました。これからは、搾乳ロボットの持つ「省力化」、「個別管理化」、「データ蓄積と飼養管理への応用」といった特徴を、その地域の酪農場の実態に合わせて活用するよう飼養管理が工夫されるでしょう。
搾乳ロボット利用法は、世界各地でますます多様化し、世界のどこかで発達したローカルな飼養管理法が、自分自身の条件や目標とベストフィットすることがあります。自動搾乳システムの飼養管理は日々進化しています。固定観念にとらわれない姿勢こそが大切です。またSNSを通じて、地域や場所に捉われない技術的情報の交流が、現在、盛んとなっています。そうした交流から、自分に合った搾乳ロボット利用法を、酪農家自身が情報発信しつつ見出すという姿勢は、技術の新しいステージを迎えるのにとても大切です。




 この作品はクリエイティブ・コモンズ 表示-非営利 4.0 国際ライセンスの下に提供されています。
この作品はクリエイティブ・コモンズ 表示-非営利 4.0 国際ライセンスの下に提供されています。