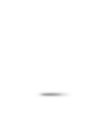草地の土づくり ≪第5回≫土壌診断に基づく施肥対応1:土壌採取時の注意と施肥対応の考え方
掲載日:2020.05.13
酪農学園大学 農食環境学群 循環農学類
教授 三枝 俊哉

はじめに
前回は、北海道の寒地型草地に対する施肥計画の基本となる「北海道施肥標準」についてご説明しました。利用形態、草種構成、採草地では地帯や土壌ごとに年間の標準的な施肥量が定められていましたね。そして、この北海道施肥標準は、①土壌の肥沃度が標準的な圃場に必要な年間施肥量であること②草地土壌の肥沃度は管理来歴によって圃場ごとに異なること③それゆえ、定期的に土壌診断をおこなって、各圃場の肥沃度を評価し、施肥量の補正をおこなう必要があること―をご紹介しました。
ここからは北海道の維持管理草地における土壌診断のやり方と施肥量の計算方法を具体的にご紹介します。まず、最初に草地土壌の採取方法について解説します。その後、土壌診断による肥沃度の判定、それに基づく施肥量の調整方法に関する一般的な考え方をご説明します。実は、土壌診断による肥沃度の判定方法や施肥量の計算方法は、養分の種類や土壌型によって異なります。本稿で一般論を概説した後は、次回から養分ごとにその特徴を解説していきたいと思います。
1.土壌採取時の注意
土壌診断で土壌を採取する際、重要な注意点が三つあります。土壌を採取する深さ(採土深)、1圃場からの採取点数、そして採取時期です。この注意が守られないと、分析をどんなに正確におこなっても、その圃場の肥沃度を正しく評価することはできません。
(1)維持管理時の採土深は0~5cm
以前、草地土壌の特徴をご紹介した際(第2回草地土壌の特徴)、草地への肥料養分は草地表面に施用されるので、土壌養分含量は表層に近いほど急激に高まり、下層では低い値となることをお話ししました(図1)。同じ肥沃度の圃場でも、表層の土壌と下層の土壌では、土壌養分含量が大きく異なります。つまり、どこの土を採取したかで、その圃場の肥沃度の評価が変わってしまいます。
そこで、維持管理草地では、表層0~5cmの土壌を採取することになっています(図2)。時には表層にルートマットと呼ばれる地下茎と根でできたマット状のものが形成されている場合もありますが、それも含めて表層から5cmまでの層位を採取します。ときどき、「ルートマットは土ではない」と考え、ルートマットを外し、その下の土壌を採取される人がいます。しかし、これは誤りです。ルートマットの中にも土は含まれますし、何よりも、現在の草地の土壌診断基準値は、どの養分でも、ルートマットを含む0~5cmの土壌分析値に基づいて設定されているからです。
(2)1圃場からの土壌採取点数
草地の土壌養分は毎年耕起する畑地などと異なり、場所によるばらつきが大きいです。統計学を使うと、理論上、10haの採草地で200~500点もの土壌採取が必要という計算も成り立つことがわかっています。しかし、これを日常業務にするのは大変です。道総研根釧農業試験場(現 酪農試験場)で2008~2013年に実施した例では、0.4ha~11.4haの採草地、放牧草地など35圃場に対し、1圃場20点前後を目安に土壌を採取し、よく混合して1点/圃場とすることにより、施肥管理の違いが土壌化学性に与える影響を把握できています(Saigusa et al 2018)。
それにしたがって土壌採取作業をおこなう場合、まず、極端な土壌養分含量が予想される場所は採取対象から除外します。たとえば圃場の「取り付け」や「まくら地」周辺は肥料が多く落ちやすいです。水が集まる場所も土が溜まったりえぐれたりして、極端な土壌養分含量になりやすいでしょう。これらの場所を避けつつ、圃場の対角上を歩測で等間隔に、面積に応じて全体から20点前後採取して1袋に混合します。こうすれば、一筆書きを描くように複数の圃場から連続的に効率よく土壌を採取できます(図3)。
(3)土壌の採取時期
維持管理時の草地で土壌診断をおこなう場合、翌年の牧草生産に向けた施肥管理を計画したいのですから、それがおこなわれる前の土壌養分状態を把握したいです。かつては早春施肥前の土壌採取が推奨されました。しかし近年は、秋に堆肥やスラリーなどの自給肥料が大量に施用されることが増えました。この秋施用は、翌年1番草に対する施肥となるので、近年の理想的な土壌採取時期はその前まで、すなわち、草地の最終利用後から秋の肥培管理がおこなわれる前までの間が適切です。化学肥料や自給肥料の施用直後は、養分が溶け出して土壌に浸透する過程が均一には進まないので、分析値のばらつきが大きく、圃場全体の代表値を判断しにくいのです。
2.土壌分析値の見方と使い方
草地に化学肥料や堆肥などの資材が投入されると、その中の肥料養分が土壌に含まれる水に溶け出します。こうして土壌中には、もともとの土壌養分と肥料由来の養分が混在するようになります。牧草にとっては、根から吸収する養分が何に由来していてもよいので、土壌養分含量が多ければ施肥量は少なくて済み、土壌養分含量が少なければ沢山の肥料が必要になります。つまり両者の関係は、図4の点線で示したように連続的に変化します。典型的な例として、火山性土に立地したチモシー採草地のカリウムの場合があります。詳細は次回に述べますが、図4の縦軸を「基準収量を得るために牧草に必要なカリウムの総量」、横軸の「土壌から供給される養分量」を草地の表層0~5cm土壌中に存在する交換性カリウム量とすることにより、個々の圃場に施肥すべきカリウムの量を計算できます。一方、窒素やリンは、土壌中でその形態を複雑に変えるため、火山性土のカリウムのように単純に計算できません。そこで、多くの場合、図4の赤線のように階段状に施肥対応を設定します。赤線が土壌診断基準値の範囲内の時、その圃場には北海道施肥標準の施肥量をそのまま施肥します。一方、その両脇のように、土壌養分含量の不足域には施肥標準量よりも施肥量を増やす(増肥)施肥対応、土壌養分含量の過剰域には施肥標準量よりも施肥量を減らす(減肥)施肥対応が処方されます。この模式図では3段階ですが、肥料養分の種類や土壌条件によっては、増肥や減肥の段階を増やし、より連続的な変化に近い施肥対応も設定されています。
<引用文献>
松中照夫・三枝俊哉(2016)草地学の基礎-維持管理の理論と実際-,p129-132,農山漁村文化協会,東京.
Saigusa T, Matsumoto T, Osaka I, Minezaki Y (2018) Improved manure and fertilizer practices changes nutrient dynamics in silage meadows on a dairy farm in eastern Hokkaido, Japan.Grassland Science 64(4) 259 – 268






 この作品はクリエイティブ・コモンズ 表示-非営利 4.0 国際ライセンスの下に提供されています。
この作品はクリエイティブ・コモンズ 表示-非営利 4.0 国際ライセンスの下に提供されています。