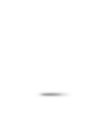環境にやさしい牛の飼い方とは―ルーメン環境を最適化すると環境負荷は低減する―
掲載日:2018.10.30
酪農学園大学 農食環境学群 循環農学類
教授 泉 賢一

1.牛と環境の関係
放牧地で寝転び、おいしそうに草をそしゃくする乳牛。一見すると自然と調和した“エコ”な風景として映ります。ある条件の下でそれは正しいのですが、条件によっては決してエコとはいえない状況が発生します。乳牛は1日に50kgのふんと15kgの尿を排せつします。これを合わせると1日1頭当たり65kgになります。
ここに平均的な酪農場があるとしましょう。搾乳牛50 頭と育成牛30頭を飼養し、毎日、搾乳、飼料給与、そしてふん出しを行います。育成牛は2頭で成牛1頭分のふん尿と換算すると、この酪農場のふん尿排せつは1日で65kg×(50頭+15頭)=4,225kgとなり、年間では何と4,225kg×365日=1,542tに達します。実際には、残飼や敷料もふん尿と混合され排せつされるので、酪農場全体の排せつ物量はこの数字よりも多くなるでしょう。
この年間1,500tものふん尿をどのように処理すべきなのでしょうか。ホームセンターに行くと牛ふん堆肥が売られており、家庭菜園の愛好家にとっては欠かすことのできない天然肥料となっています。もしくは、排せつされたふん尿を畑にまいて(還元して)、全量が牧草や飼料作物の肥料として利用されれば、まさにクリーンでエコな酪農生産になるでしょう。問題となるのは、これだけ大量に生み出されたふん尿をまくだけの畑がないケースです。ふん尿散布量の基準値はふんと尿を混合したスラリーの場合、10a当たり4~6tとされています。計算を簡略化するため、この酪農場が所有する畑が30haで10a当たり5t散布とすると、ふん尿散布可能量は30ha×10×5t=1,500tとなります。若干“おまけ”してもらえば、この酪農場の年間排せつ量はかろうじて範囲内に収まったとみてよいでしょう。しかし、まとまった土地面積を有さない経営も少なくありません。このようなケースでは畑作・園芸農家などに引き取ってもらうなど、やりくりに苦慮することになります。
2.ふん尿中の環境汚染物質
さて、ふん尿を過剰に土地にまくと、何が環境にとって悪いことなのでしょうか。工場からの化学廃棄物ではなく、ふん尿は牛という生物が出す天然物質です。天然物質であれは少々過剰に土地にまいても問題ないのではないでしょうか。
家畜のふん尿中にはさまざまな元素が含まれますが、そのうちの窒素(N)とリン(P)は主要な肥料成分です。NとPが植物体に吸収されるのであれば何ら問題はありませんが、植物体が吸収し切れなかった部分については地下水や河川に流出してしまいます。水系に入り込んだNやPは、富栄養化をもたらす汚染源となってしまいます。また、Nについては空気中にも揮散してしまい、酸性雨の原因物質にもなり得ます。
水や大気中にひとたび放出されてしまうと、環境汚染物質は広範囲に拡散してしまうので、事は一酪農場だけの間題では収まらなくなってしまいます。日本のように四方を海に囲まれた島国であれば“水に流す”という発想も通用しますが、周りを他国に囲まれているヨーロッパでは、自国の汚染物質が河川や雨で隣国に運ばれてしまうと国際間題にも発展しかねません。このため、家畜ふん尿の適正管理が厳しく求められています。筆者は1999年にデンマーク、オランダ、ドイツを訪問しましたが、その当時から家畜からの汚染物質排せつを減らすための研究が行われていたり、ふん尿散布基準が厳しく制定されていたことに驚きを感じました(泉ら, 2000)。
前置きが長くなりましたが、本稿では飼料栄養価のバランスやルーメンの健康を意識した「環境にやさしい酪農」について考えてみます。
3.ルーメン微生物と窒素の関係
乳牛が摂取する飼料中には、炭水化物や脂肪のほかにタンパク質が含まれています。タンパク質は乳や肉の生産、あるいは後述するルーメン微生物の増殖にとって欠かすことのできない栄養素です。先に触れた環境汚染源となり得るNは、このタンパク質に含まれています。
飼料に含まれるタンパク質は、牛に摂取されてルーメンに到達すると、ルーメン内に無数に存在する微生物が殺到して細かく分解されてしまいます。タンパク質はNを含むアミノ酸が連なったものですが(図1)、微生物はタンパク質をアミノ酸、そしてさらに小さな分子であるアンモニア(NH3)へと分解します(図2)。微生物は分裂によって増えますが、微生物はアンモニアを餌としており、自らが増殖する際の体(タンパク質)をつくることに利用しています。また、微生物が分解や増殖するためにはエネルギーが必要ですが、そのエネルギー源としては炭水化物が使われます。炭水化物の中でも、特に分解が容易なでんぷんや糖が微生物にとっての格好のエネルギー源となります。
タンパク質と炭水化物、そのいずれかだけでは微生物は増殖できません。両方の存在が必要です。この関係を身近な所に置き換えてみます。筆者はよく回転寿司を食べに行きますが、皆さんはいかがでしょうか。寿司は、シャリとネタがセットになって初めて寿司となります。コンベアの上をシャリだけ、あるいはネタだけが回ってきても“ぎょっ”とするだけではないでしょうか。ネタをタンパク質、シャリを炭水化物、そして寿司を微生物と置き換えると、回転寿司店と同じことがルーメン内でも行われていることが分かります。ネタが5貫分あっても、シャリが3貫分しかなければ、寿司は3貰しか握ることができません。無駄になったネタ2貫分は廃棄することになり、すし店の経営にとっては痛手となります。ルーメン内の微生物増殖も単純にいってしまえば同様のメカニズムになっており、飼料の栄養バランスが悪いとタンパク質飼料は無駄になってしまい、N排せつ量の増加による環境負荷につながります。
では、利用されなかったタンパク質はアンモニアに分解された後、どうなってしまうのでしょうか。アンモニアは通常は気体で存在している有毒なガスです。人間も高濃度のアンモニアガスを吸入すると、命にかかわってしまうほどです。微生物に利用されなかったアンモニアは、ルーメンの粘膜から牛の体内(血液中)に吸収されます。吸収されたアンモニアは猛毒なので、肝臓に送られて無毒な尿素に変換されます(図2)。この過程で、牛は多くのエネルギーを消耗してしまいます。血液中の尿素は尿や乳中に溶け込んで体外へ排せつされるか、唾液に混入したり、直接ルーメンに分泌されます(乳中に溶け込んだ尿素については重要なので後述します)。
アンモニアが尿素に変換されてもNは含まれたままです。微生物に利用されずに無駄になるアンモニアが多ければ多いほど、尿素として尿中に排せつされるN量も多くなります。無駄になるアンモニアが多いということは、高価なタンパク質飼料が無駄になってしまうことを意味します。昨今、高タンパク飼料の価格高騰が著しいので、できるだけロスの少ない給与法が求められます。
4.窒素利用効率を向上させる飼料設計
乳牛がどれぐらい効率良く窒素を利用しているかを知るための便利な指標が、先ほども出てきた乳中に含まれる尿素の濃度(MUN=乳中尿素態窒素)です。この値は、バルク乳の成分報告値や検定成績に記載されているので簡単に知ることができます。MUNが高ければ、ルーメン内で微生物に利用されず無駄になるアンモニアが多いことを表しており、タンパク質の供給過剰か、エネルギーの不足を意味しています。
高過ぎるMUNを適正範囲内に収めるためには、飼料中のエネルギー含量を高めるか、タンパク質の給与水準を低くする必要があります。飼料設計を見直すことでタンパク質含量を17%から13%に低下させた研究では、乳生産に影響することなくMUNが1dL中14.3mgから同7.3mgに低下し、1日のN排せつ量も125gから69gへと激減しました(扇, 2004)。N排せつの減少分は1日1頭当たりで見るとわずか56gと思うかもしれませんが、前述した架空の酪農場で年間に換算すると1,329kgのN削減に相当します。蛇足ですが、筆者の口癖に「酪農は掛け算」があります。酪農の現場では「取るに足らないもの」と見過ごしがちなものであっても、それが積算されると経営に大きく影響することが多く見られます。
MUNの適正範囲は出典によって異なりますが、バルク乳では多くの場合1dL中10~14mg程度が推奨値とされています。適正範囲を上回ったケースについては、これまで繰り返し述べてきたように牛にも経営にもやさしくないので早急に改善が必要です。では、それを下回ったケースではどうでしょうか。筆者は経験上、MUNが1桁台であっても乳生産に影響しないことを認めています。先の扇(2004)の研究も同様の結果を示しています。MUNは高価なタンパク質飼料が無駄に排せつされる指標ともいえるので、適正範囲を下回ったからといって拙速に高める必要はないと考えます。ただし、その場合でも牛の状況やバルク乳の成分についてより一層の観察が必要になることは言うまでもありません。
MUNに影響するそのほかの要因として、最後に飼料中のアミノ酸バランスについて触れます。米国の最新の飼料設計の考え方では、乳牛に供給するアミノ酸のバランスを最適化することでNの利用効率を高めることが提唱されています。タンパク質は多数のアミノ酸が連結してつくられていますが、幾つかポイントとなるアミノ酸があります。そのアミノ酸が不足すると、ほかのアミノ酸がどれだけあったとしても目的とするタンパク質をつくることができません(図3)。これを「制限アミノ酸」といいますが、自動車の組み立てで例えてみると分かりやすくなります。タイヤ、エンジン、ボディー、ヘッドライト、ドア、ガラス、シート、これらの部品はふんだんにあるのですが、ハンドルがありません。タイヤが6本あっても、エンジンが2機あっても、たった一つのハンドルがないと自動車を組み立てることができず、ほかの部品はすべて無駄になってしまいます。このハンドルに相当するのが「制限アミノ酸」です。乳牛ではメチオニンやリジンが制限アミノ酸になるケースが多く、これらのアミノ酸が不足しないように飼料設計を見直すことでNのロスを抑制できる場合があります。
5.健康なルーメンとは
ここまで、①Nの排せつ過剰は環境への負荷となる②それを防ぐためには飼料中のタンパク質とエネルギーのバランスを取る③そうすることでルーメン微生物の増殖効率が高まる―ことを解説してきました。しかし、衣・食・住という言葉があるように、飼料の栄養バランスさえ取れていればルーメン微生物にとって良好な住環境であるといえるでしょうか。
ルーメンは巨大な臓器であり、その内部には膨大な量の飼料が蓄えられ、日夜休むことなく飼料の発酵が続いています。ルーメン内は、上部(背側)のガス層とその下に位置する内容物層に分けられます(図4)。内容物の層は、上部のルーメンマットとその下側(腹側)の非マット層に分けられます(写真)。粗飼料などの粗く軽いものは固く絡まり合い、ルーメンマットを形成して内容物上部に浮遊します。穀類などの比重の重いものは液状の非マット層に沈み、胃運動によって第三胃以降に通過していきます。このルーメンマットがルーメン壁を機械的に刺激することにより、反すうが引き起こされます。ルーメン壁に対する接触刺激が少ない場合、すなわち粗飼料給与量が少なく、硬いルーメンマットが形成されないケースでは反すう時間は減少します。
反すうは、ルーメン微生物の住環境を良好にすることから極めて重要です。反すうが行われると大量の唾液が分泌されます。唾液はアルカリ性であり、pHの低下を抑える働きがあります。このため、反すう時に唾液がルーメン内に流入することにより、発酵によって生成された酸が中和され、ルーメン内のpH低下を予防しています。ルーメンpHの低下は微生物数を減少させることにつながるので、唾液の流入はルーメン環境を健康に保つために必要です。つまり、ルーメン微生物にとって快適な住環境は、硬く充実したマットが形成されたルーメンということになります。このようなルーメンでは微生物の活性が高まり、無駄に排せつされるNも減り、環境に対しても経営にとっても好ましいものになります。
ふん尿による環境汚染でイメージするのは堆肥盤から流れる排汁だったり、畑に過剰に投入される堆肥だったりと、牛舎施設や土地といったスケールの大きな光景が目に浮かびがちです。しかし、餌のバランスを考えることで1頭の牛からのN排せつ量をg単位で抑制するといった、一見地味に見えるが実は効果的な方法もあることを頭の片隅においていただきたいと思います。
<参考文献>
泉賢一・上野秀樹・松原久夫(2000)「ヨーロッパにおけるバイオガスプラントを視察して」酪農学園大学エクステンションセンター,酪農ジャーナル59(9):26-29.
薗田勝(2013)「マンガでわかる栄養学」こやまけいこ作画,ビーコムプラス製作,オーム社.
花田正明(2010)「ルーメン内分解性からみた粗蛋白質の分類―乳牛栄養学の基礎と応用」増子孝義・花田正明・中辻浩喜編著,デーリィ・ジャパン社.
扇勉(2004)「泌乳牛のアミノ酸栄養改善による窒素排泄量低減に関する研究」北海道立農業試験報告.
佐藤弘之・新里出(2002)「シリーズ“アミノ酸”No.14.飼料へのアミノ酸の利用」食と健康の情報誌, Ajico News No.205,味の素株式会社広報部.







 この作品はクリエイティブ・コモンズ 表示-非営利 4.0 国際ライセンスの下に提供されています。
この作品はクリエイティブ・コモンズ 表示-非営利 4.0 国際ライセンスの下に提供されています。