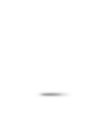草地の土づくり ≪番外編≫牛、馬、羊もこれ一本!放牧草地の施肥管理
掲載日:2024.03.15
酪農学園大学 農食環境学群 循環農学類
教授 三枝 俊哉

はじめに
2024年1月、農研機構北海道農業研究センター(2024)より、これまでの北海道施肥標準(北海道農政部 2020)における放牧草地の施肥管理を大きく進化させる技術が北海道農業試験会議(成績会議)に提案され、指導参考事項に採択された後、同年2月の農業新技術発表会で発表されました(共同研究機関:酪農学園大学;協力機関:道総研酪農試験場、畜産試験場、家畜改良センター十勝牧場、JRA日高育成牧場)。この技術には、共同研究機関である当研究室で取り組まれた7年分の卒業論文が大きく関わっており、本学園フィールド教育研究センター肉畜生産ステーションの肉牛放牧草地で得られた調査結果がその根幹の一部を構成しています。そこで本稿では、新しくなる放牧草地の施肥管理技術についてご紹介します。
1.どんな技術か?
この技術は、その年の放牧計画を立案した時点で具体的な施肥設計を実現できるようにしたものです。また、ウシでもウマでもヒツジでも共通の方法で算定できます
これまでの施肥標準も、主に搾乳牛の集約放牧を対象とした草地の養分動態調査に基づいて設定されていました(図1;根釧農試他 2008;三枝ら 2014)。しかし、この時に実測したのは養分摂取量だけで、ふん尿排泄による養分還元量は既往の文献値を引用していました。したがって厳密には、搾乳牛の集約放牧ではない放牧条件について、適用の妥当性を確認する必要性が残されていました。また、放牧草地に必要な施肥量が被食量(家畜が放牧期間中に食べる草の量を面積当たりで示した数値)によって変化することも分かっていました。しかし、農家に被食量の把握を求めることが現実的に難しかったので、平均的な被食量の中で標準施肥量に幅を持たせ、その範囲を参考にして、農家自身で牧区ごとの標準施肥量を把握してもらうという、曖昧な表現を採用していました(図1)。このあたりの詳細は酪農PLUS+「草地の土づくり第4回施肥基準とは何か?」をご覧下さい。
本技術は、その被食量を、農家が圃場を調査することなく、放牧家畜群の月齢構成と頭数そして牧区ごとの放牧計画から想定し、それに応じて施肥量を決めることができるようにしました。さらに、その適用範囲をウシだけでなく、ヒツジとウマにも拡大しました。
2.どのように開発されたか?
(1)ウシ放牧草地における養分動態の実測
まず、ウシ放牧草地の養分動態を複数の異なる放牧条件で実測しました(図2)。被食量は従来から行っていた草地調査で把握しました。また、放牧牛のふん尿排泄量の把握には、農研機構北海道農業研究センターが有していた全量回収法を用いました。そして、2015年と2016年は同センターにおける乳用育成牛の全日・連続放牧条件で、2017年と2018年は酪農学園フィールド教育研究センター肉畜生産ステーションにおける肉用繁殖・育成牛の全日または時間制限の輪換または連続放牧条件で、放牧草地の被食量とふん尿排泄量を実測しました(図2)。その結果、放牧草地に必要な施肥量は、乳用、肉用といったウシの品種、繁殖、育成などの月齢、輪換、連続などの放牧方法が異なっても、主に搾乳牛の集約放牧を対象とした先行研究(根釧農試他 2008)と共通の回帰式を設定できました(図3;Okuiら 2021)。この時点では今までと同様で、被食量がわからないと必要施肥量を決めることができません。しかし今回、各牧区の放牧期間中に放牧牛の体重を把握していたおかげで、年間その牧区に放牧されたウシの体重を積算した面積当たりの値(時間制限放牧では体重に放牧時間割合を乗ずる、以下、放牧期延べ体重kg/ha)の平均2.38%相当量を、年間の被食量(乾物)とみなすことができるという見通しを得ました(Okuiら 2021)。
(2)他地域の実規模放牧草地で実証
本来、放牧牛の採食量や養分排泄量は畜種、品種、体重などによって、それぞれ異なることがよく知られています(農業・食品産業技術総合研究機構 2009,2017)。したがって、それでもあえて被食量を放牧期延べ体重の2.38%とみなしてよいか、また、よその土地や別の牛群でも同じように必要施肥量の見積もりができるか否か、確認する必要がありました。そこで、道総研の酪農試験場(中標津町)には2009~2011年におけるホルスタイン種育成牛の牧区ごとの放牧履歴と土壌養分含量のデータを使用させて頂き、畜産試験場(新得町)では2019年に肉用種(黒毛和種、アバディーンアンガス種、両品種の交雑種)繁殖および育成牛の放牧草地で放牧履歴と土壌養分含量の調査をさせて頂きました。こうして、北農研センターと酪農学園で開発された必要施肥量推定式が他の実規模放牧草地でも同じ回帰式が成り立つかどうかを実規模の放牧条件で検証しました(三枝ら 2022)。
いずれの試験場でも放牧牛の体重は定期的に測定しているので、放牧履歴から放牧期延べ体重を正確に算出できます。これの2.38%が被食量の推定値です。推定した被食量の値を図3の推定式に代入すると、窒素、リンおよびカリウムの必要施肥量が算出されます。これが放牧によって消費される肥料養分量に相当します。施肥実績(実際に施肥された量)からこの必要施肥量を差し引くと、放牧期間中における草地の養分収支を見積もることができます。すでに、先行研究(三枝ら 2014)により、土壌養分含量の評価に培養窒素(畑地培養法、30℃4週間)、有効態リン(Bray No.2、土液比1:20、20℃)、交換性カリウム(1M酢酸アンモニウム(pH7)抽出法)を用いることで、放牧草地の養分収支と放牧前後における土壌養分変化量の散布図を描くと、各牧区のデータがy=xの周辺に一定の誤差範囲をもって分布することが知られています。調査の結果、いずれの放牧草地でも両者は先行研究(三枝ら 2014)と同程度の誤差範囲(RMSE)を伴っておおむね良好に対応し、図3の必要施肥量算出法が異なる地域の実規模放牧草地でも成立することがわかりました(図4)。さらに、その際使用する体重には、平均月齢に対する標準体重を使っても大きな誤差が生じないことも確認できました(図5)。放牧農家は、放牧牛の体重は測定していなくても、牛群の月齢構成は把握しているはずです。これにより、ウシの放牧草地では、放牧牛群の月齢構成とその年の放牧計画が立案できたら、その時点で各牧区の年間施肥量を算定できるようになりました(表1)。
(3)ヒツジとウマの放牧草地への適用拡大
ヒツジとウマの放牧草地に表1を適用し、その妥当性を図4と同じ方法で検証しました。めん羊(サフォーク種)は家畜改良センター十勝牧場(音更町)とB牧場(道北地域A町)、ドサンコ(北海道和種)は道総研畜産試験場、軽種馬(サラブレッド種)はJRA日高育成牧場(浦河町)にご協力を頂き、各放牧草地で牧区ごとに放牧履歴と土壌養分含量の調査をおこないました(図6)。ヒツジもウマも、放牧草地の養分収支と放牧前後の土壌養分変化量はウシの放牧草地と同程度の誤差範囲を伴っておおむね良好に対応しました(図7)。つまり、ヒツジの放牧草地でも、ウマの放牧草地でも、ウシと同じように表1を使った施肥設計が可能となりました(北海道農業研究センター 2024)。
3.どのように使うか
表1の使い方を説明します。放牧家畜群の体重は実測値を平均するか、放牧期間中の平均月齢における標準体重を用います。月齢別の標準体重は、表2に示す各畜種の飼養標準(農林水産省農林水産技術会議事務局 1996;日本中央競馬会競走馬総合研究所 2004;農業・食品産業技術総合研究機構 2009,2017)で参照できますし、その根拠となる推定式から計算することもできます。放牧家畜群の平均体重が計算できたら、各群をどの牧区で年間何日放牧するかの計画に基づき、表2の式①で放牧期延べ体重を算出します。また、これを500kgで割り算すると、体重500kg換算延べ放牧頭数が求められ、公共牧場でよく使われるCD(カウデー)という単位になります。公共牧場の職員さんの中には、式①の計算などしなくても、自分の担当する牧区が何CDの牧養力を有するか、把握していらっしゃる方も多いと思います。あとは、マメ科牧草が多いか少ないかで窒素施肥量を選びます。
現在の北海道施肥標準(北海道農政部 2020)の数値を図1で見れば、表1の300~500CDの放牧草地を対象としていることがわかります。ヒツジやウマの放牧圧はウシの集約放牧よりも低いことが多いので、今までの施肥標準では対応が困難でしたが、本技術により必要施肥量を適正に見積もれるようになりました。一方、道央・道南のように気象条件が良好で放牧期間の長い地域で集約的な放牧を行うと、700CDに至る事例も計算上ないとは言い切れません。しかしその場合、環境保全に配慮した放牧圧の上限(成牛2.5頭/ha、天北農試 2007)を超過する危険性が高いので、表1では上限を600CDとしました。
年間施肥量が決まったら、放牧草への硝酸塩の蓄積を防止するため、1回あたりの窒素施肥量の上限が30kg/ha程度となるように施肥回数を決め、表に示された施肥時期に均等に分施します。また、兼用利用の場合には、採草利用時に対しては採草地の施肥対応、放牧利用時にはその期間に想定される延べ体重に応じて施肥量を見積もればよいので、どの番草までを採草し、いつから放牧するか、自由な計画が可能になりました。
なお、この技術は放牧家畜の採食とふん尿還元が正常に繰り返される条件で成り立っているので、これが保証できない放牧管理には適用できません。たとえば、1日2~3時間の時間制限放牧のように1回の放牧時間が極端に短い場合には、採食行動が卓越して十分なふん尿還元量が期待できないため、適用困難です。また、ウマの放牧草地では放牧草地から除糞する事例がみられます。夏季に除糞されると、採食量に対して排泄量が少なくなりすぎ、適用が難しくなります。一方、冬季に牧区内で給餌しながら運動のために放牧をおこなった場合には、春の放牧開始までにふんを収集・搬出し、冬期間に外から持ち込まれた養分を牧区から除去すれば、本技術の適用が可能です。
おわりに
本技術によって、農家が放牧家畜群の月齢構成とその放牧計画を立案した時点で、これまで以上に具体的な年間施肥量を参照できるようになったことは、北海道の放牧草地における施肥管理技術の大きな進歩といえます。これは、本来、体重や畜種、品種によってそれぞれに異なる体重当たりの採食量や養分排泄量を、あえて一律に設定し、必要施肥量の求め方を単純化したことによります。現在の精密な飼養管理技術が、採食量や排泄量の体重間差、品種間差、畜種間差をふまえて構築されていることを考慮すれば、家畜管理のために諸係数を精密に場合分けすることの重要性に疑う余地はありません。本技術の最も重要な特徴は、従来設定されてきた採食量や排泄量の体重間差、品種間差、畜種間差を否定するものではなく、それらが生産現場の放牧草地に対する施肥対応の係数を変更するほどの大きさを持たないことを明らかにした点にあります。この技術が必要最小限の肥料資源による持続的な放牧草地の養分管理に役立てば幸いです。
<参考文献>
北海道農業研究センター(2024)ウシ、ウマ、ヒツジ用草地の放牧利用計画に基づく必要施肥量算定法.令和6年普及奨励ならびに指導参考事項,北海道農政部,札幌
https://www.hro.or.jp/upload/assets/list/agricultural/center/kenkyuseika/gaiyosho/r6/f2/10.pdf
北海道農政部(2020)北海道施肥ガイド2020.北海道農政部,札幌,192-194
https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ns/shs/clean/
上川農試天北支場(2007)環境保全的な放牧の目安となる牧区単位の適正放牧密度.平成19年普及奨励ならびに指導参考事項,北海道農政部,札幌
https://www.hro.or.jp/agricultural/center/result/kenkyuseika/ippan19.html
根釧農試・上川農試天北支場・北海道農研センター(2008)養分循環に基づく乳牛放牧草地の施肥対応.平成20年普及奨励ならびに指導参考事項,北海道農政部,札幌
https://www.hro.or.jp/list/agricultural/center/kenkyuseika/gaiyosho/h20gaiyo/f2/2008237.htm
日本中央競馬会競走馬総合研究所(編)(2004)軽種馬飼養標準(2004年版).日本中央競馬会競走馬総合研究所,東京,p11-100
農業・食品産業技術総合研究機構(編)(2009)日本飼養標準・肉用牛(2008年版).中央畜産会,東京,p80-82,120-125,194-200
農業・食品産業技術総合研究機構(編)(2017)日本飼養標準・乳牛(2017年版).中央畜産会,東京,p56-57,86-90,133-136
農林水産省農林水産技術会議事務局(編)(1996)日本飼養標準めん羊(1996年版),中央畜産会,東京,p12-35
Okui T, Yagi T, Yamada K, Niwa Y, Asai K, Kumagai T, Yoshida Y, Hori K, Ugaki R, Yamashita S, Kato Y, Tsukasaki K, Saigusa T(2021)Nutrient dynamics under different regimes of stocking and cattle type of temperate pastures in Hokkaido, Japan.Grassland Science 67:102-117
三枝俊哉・金田学・小田島究路・西道由紀子・松本武彦・大坂郁夫(2022)北海道のウシ放牧草地における放牧期延べ体重に対応した施肥適量.日本草地学会誌 68:73-84
三枝俊哉・西道由紀子・大塚省吾・須藤賢司(2014)北海道の乳牛集約放牧草地における養分循環に基づく施肥適量,日本草地学会誌 60:10-19
<「草地の土づくり」シリーズ>
第1回 草地更新時の注意点
第2回 草地土壌の特徴
第3回 草地の維持管理の基礎
第4回 施肥基準とは何か?
第5回 土壌診断に基づく施肥対応1:土壌採取時の注意と施肥対応の考え方
第6回 土壌診断に基づく施肥対応2:カリウムの施肥対応
第7回 土壌診断に基づく施肥対応3:リンの施肥対応
第8回 土壌診断に基づく施肥対応4:窒素の施肥対応
第9回 自給肥料をどう使うか?
第10回 酪農場における施肥改善の実証事例
第11回 地域で適切な養分管理を進めるために








 この作品はクリエイティブ・コモンズ 表示-非営利 4.0 国際ライセンスの下に提供されています。
この作品はクリエイティブ・コモンズ 表示-非営利 4.0 国際ライセンスの下に提供されています。